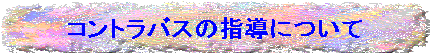
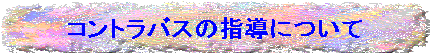
このページの最終更新日:03/03/15
最初に
コントラバスを専門に勉強したわけでもない私がこのようなことを堂々と発表することに少々とまどいを覚えますが、あまりにひどい現状を何とかしようと、敢えて書きます。もちろん教則本ではないので、順を追って丁寧に解説してあるわけではありません。(そのようなことができる力量を持っているわけではありませんので)ただ、いわゆる吹奏楽指導者の「全く手がかりがない」状態を、何とかしようとしているだけです。(こういうことができるのがインターネットのよいところだと考えています)
体の大きさに合った楽器を
特に中学校の吹奏楽のコントラバス奏者の中には、体に合わない(大きすぎる)楽器を使っている子が多く見られます。3/4くらいの小さめの楽器を使わせるか、それだけの予算的な余裕がないなら、はじめから体の大きな子を選ぶかする必要があります。大きすぎる楽器では指に負担がかかってしまい、いくらがんばってもきちんと弾けるようにはなりません。そうなると、本人にとっても指導者にとっても悲劇的な結果しか生まれません。無茶なことを言っているようですが、本当に基本的なことです。
教則本について
コントラバスは、弦楽器です。そして、吹奏楽においては唯一の弦楽器です。自然、管・打楽器とはまったく奏法の基礎が違います。ここのところを押さえていない吹奏楽指導者が、多いのではないでしょうか。指導法が解らなければ、自分で教則本を買い込んで読んでみればよいのです。どんな教則本がよいか解からないなら、楽器屋さんに相談すればよいのです。楽器屋さんも解らなければ、そこは商売ですから、何とかどこかから調べてくるはずです。(楽器屋さんというのは、そういう風に利用するものです)それさえしないで「解らない」とばかり言っていたのでは、生徒に合わせる顔がないのではありませんか。ちなみに私は、初期には「Simandl」の教則本を使いました。現在は日本語版も出ているようです。くわしくは、「教則本について」のページをご覧ください。
左手の指の使い方について
コントラバスは、左手の指を独立させて弾きます。上の「吹奏楽におけるコントラバス」にも書いておきましたが、ここのところが解っていない指導者が多いようです。指と番号は、下の表のとおりです。なお、ピアノで使う指番号とはずれていますので、ピアノを弾く子には十分注意させるようにしてください。普通(低いポジション)、「1・2・4」の指を使います(教則本によっては、「1・2・3」を使うようになっているものもあります。イタリアではそのようにするということですが、標準的な日本人の指では、ちょっとつらいと思います。ですから、教則本を選ぶときには、必ずこの項目を確かめてから購入するようにしてください)。そしてそれぞれの指の間が「半音」の間隔になるようにします。なお、親指の番号が「0」ですが、開放弦も同じように「0」で表します。音を見ればわかりますが、注意してください。(写真1参照)
| 親指 | 0 | 吹奏楽では、ほとんど使わない。 |
| 人差し指 | 1 | |
| 中指 | 2 | |
| 薬指 | 3 | 吹奏楽では、滅多に使わない。 |
| 小指 | 4 |
右手の使い方について
右手の弓の持ち方については、教則本および下の写真を参考にしてください。注意する点としては、親指は腕の力(重さ)をきちんと弓に伝えるようにすること、小指は弓がぶれないように添えること、その他の指には力を入れ過ぎないことです。(中指と薬指を西洋のこぎりを引くようにフロックのくびれに入れているのを見かけますが、これは絶対止めさせてください)(写真2・3参照)
| 1 |  |
左手の形です。(ハーフ・ポジション) この位置では、0(開放)と1(人差し指)との間が半音、1(人差し指)と2(中指)との間が半音、2(中指)と4(小指)との間が半音のインターバルになる。 3(薬指)は、4(小指)を使うときに補助として使う。 ここでは、「3」および「0」の指を使うポジションについては触れません。(初心者が演奏するような吹奏楽曲でこのポジションを使うことは、滅多にないからです) |
| 2 |  |
右手の弓の持ち方(ジャーマン式)です。 写真がぼやけていますが、だいたいの感じをつかんでください。 |
| 3 |  |
弓の持ち方の悪い例です。このように薬指をここに入れないように注意してください。持っているのは「弓」であって、決して「ノコギリ」ではないのですから。 |
左手の指の訓練法について
左手の指の弦の「押さえ方」についての訓練法について書いてある教則本は、寡聞にして知りません。大切なことは、弦を「押さえる」「離す」のではなく、「たたく」「はじく」ことです。音程が聞こえるくらい強く「たたいて押さえる」、同じように音程が聞こえるくらい強く「はじいて離す」訓練が大切です。こうすることで弦を押さえる力が訓練され、はっきりした音程で楽器を響かせることができるようになります。逆に言えば、この訓練をしないからコントラバスが「鳴らない」「響かない」のです。この訓練を毎日続けると、ほぼ2週間で指の皮が厚く硬くなり、物に触っている感覚がわからなくなるほどです。(私はこの時点で、リコーダーがふけなくなってしまいました。何しろ、リコーダーの穴をふさいでいるのかいないのかがまったく解らなくなってしまったのですから)しかし、一月もするとそれほどでもなくなり、指先の感覚も戻ってきます。なお、高校生ぐらいでは生意気に爪を伸ばしている子がいるかもしれませんが、この訓練のためには、ぜひとも爪を短く切らせてください。うっかりすると、爪を割ってしまうことにもなり兼ねませんので。
開放弦の弾き方
開放弦を弾くとき、指が指板から全く上がってしまう弾き方をよく見受けます。この弾き方では、ポジションがブレてしまって音程が不安定になってしまいます。できる限り、演奏に支障のない弦を押さえてポジションがブレないようにする必要があります。慣れないうちは指が疲れてしまったり無意識に押さえている弦を弾いてしまったりして混乱することもありますが、最終的にはこの弾き方を身につけた方が音程がとれる分、楽に弾けるようになります。ちょっと大変かもしれませんが、挑戦させてみてください。
このページに対するご意見ご質問は、t-kaz@intio.or.jpまで